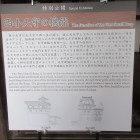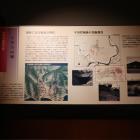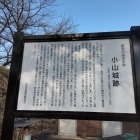平須賀城で無念の撤退をし、うめ振興館に立ち寄ってもまだ時間があったので、軽く下調べしてあった赤松城に行くことにしました。下調べによれば赤松城へのルートは2つ。北西のおたき瀧法寺からのルートは藪を突破して尾根まで直登し、尾根筋に出ても分岐が多くて迷いやすい上に距離もある…と大変そうなので、「戦国和歌山の群雄と城館」で案内されていた南麓の苗代川池からのルートでの登城です。
県道202号線から分岐に入り、工場を過ぎたあたりから道幅は狭くなります。案内には「道幅は狭く駐車可能な場所は少ないので、早めに駐車すべき」とありましたが、道沿いの畑で農作業をしている方もいたので邪魔になりそうなところには駐められず、そうこうするうちに山中に入って道幅はさらに狭くなり、先にも駐車できそうな場所は見えません。このまま進むのはマズいのでは…と思ってバックで畑まで引き返そうとするも、カーブして小川を渡る橋の縁石に乗り上げて脱輪(あわや小川に転落)しそうになり、恐ろしくてもう後退もできません。さりとてこれ以上車で進むのも怖いので、車を降りて徒歩で前方の偵察に向かうと、もうしばらく行ったところにどうにか転回できそうな箇所がありました。助かった…。今にしてみれば、転回スペースにひとまず車を駐めて、その先に駐車できそうな場所があるかどうか徒歩で確認しておけば良かったと思いますが、あの時は脱輪しかけて半ばパニック状態になり、一刻も早くこの地から脱出したいという心境だったので…。平須賀城に続いての連戦連敗にも、当面は再挑戦の意欲が湧かないほどの惨敗ぶりでした。
…ということで、赤松城の最初の投稿がこんなぐだぐだな内容で申し訳ありませんが、苗代川池からのルートで登城される場合は、道幅の狭さと駐車場所にはくれぐれもご注意下さい。
+ 続きを読む