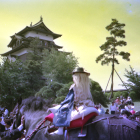午前中に新宿で知人と用事を済ませたあと、まだ時間もあるし……ということで江戸城に繰り出しました。
東京駅から和田倉門経由で大手門へ。
開館記念展開催中の三の丸尚蔵館へ行ってみると長蛇の列。係の方に何分待ちかうかがうと、日時指定の予約制かつ有料とのこと。当日券もありませんでした。
連れに「タダだよー」と大ボラを吹いてしまっていて平謝りです。
ですがやはり気になって検索してみたところ、以前(旧館時代)は無料でしたが、この秋の新館オープン後から事前予約制になり、一般料金は1,000円に設定されていました。同時に宮内庁の管轄でもなくなったようです。
実は入館の目的はもしかしたら館内からしか見えない石垣があるのではないか?という疑問を確かめることにあったのできちんと予約して改めて来なきゃなーと思っていたら、隣接する取り壊した旧館跡のゲートが開いてトラックが出てきました。
おーっ!石垣見える!!奥に見えた打込接布積みは二の丸庭園の端の部分。ここには新棟が建つそうなので今しか見られない貴重な石垣だっ!と写真撮りまくりました。
それにしても人が多いなぁと思ったらこの日は秋の乾通り一般公開の初日でした。
それならばと坂下門に向かいます。
人が多いといっても、もう以前ほどの大行列はできておらず、皇居前広場が人で埋めつくされるということもありません。
富士見櫓、富士見多聞、道灌堀と楽しみながら乾門へ。
前回来たときは西桔橋門が閉まっているのも写真に人が写り込まなくてよいなと思ったのですが、今回も閉まっていて天守台方面へ抜けられず。すてきな野面積みに近づけないのは少し残念で、これから先もうずっと通れない?のだとすると寂しい気もします。
乾門から退出後、北桔橋門から東御苑に入って、天守台、天守模型、台所前三重櫓跡展望台、汐見坂、富士見櫓と歩きまわりました。果樹古品種園にはたくさんの柑橘が実っていてとってもおいしそうでした!三つの番所をチェックして再び大手門に戻り終了。
ちょっと行くだけのつもりが2時間強の滞在となり、やっぱり江戸城は最高のテーマパークだ!と思いました。
+ 続きを読む