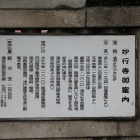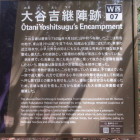重富城の投稿です。正直、後で投稿しようかと思いましたが、思うところがあって投稿させていただきます。
登城道のない謎の城で、水越峠にとりつき登れそうな場所から直登で登りましたが、正直かなりきついです。防御の仕掛けは、ほぼ無いのですが、周囲の急峻な山肌が来るものを寄せ付けません。主郭もそれほど広くなく、本当に城か❓️と訝しがりたくなりますが、登城途中に巨石が有り、周辺の扁平地に岩がゴロゴロ転がっていました。
先ほど訪れた一本松城にも石を落とすための郭がありましたが、この辺りの城の流行りなのでしょうか?
加賀城も訪問していますが、他に訪れた人がいたら先に登録していただいて構いません。
朝田さん、改めて山形県城びとの城 コンプリートおめでとうございます。
+ 続きを読む