新しい記念メダルをGETするため訪問!
松山城は好きな城郭のひとつ。天守を始め多くの遺構が残っており、小天守も木造復元されている。
また、本丸を取り囲むつづら折りになった石垣や栂門跡の20mの高石垣、長さ200mを超える登り石垣など石垣も見どころ多し。
本丸までの登城道が複数あるので、上りと下りで違うコースを選ぶのも楽しい。
+ 続きを読む

✕
人が「いいね」しています。
2026/02/14 13:42
2026/01/13 09:32
2025/12/22 13:05
四国行脚(高知→松山) (2025/04/16 訪問)
本日は、高知県から愛媛県へ移動。
愛媛の2つの国宝寺院を訪問し、昼食に松山城駐車場の近くで「鯛めし」を食す。
松山城はケーブルカーで登城。
松山は仕事で三度ほど訪問していたが、松山城は初めて。
本当なら、二の丸から歩いて本丸まで、と思っていましたが、
さすがに車での移動が続いているので、楽をしました。
四国では、あとは宇和島城と大洲城ですが、いつか行けたらいいな~
この日は、道後温泉に泊まりました。
+ 続きを読む
♥ いいね
7人が「いいね」しています。
2025/09/22 08:07
とことん?松山城(三之丸) (2025/05/18 訪問)
(続き)
翌朝、まだ暗いうちから起き出して朝食前に三之丸へ。この日の撮影はスマホだけが頼りです。三之丸は堀之内とも呼ばれるように四方を外堀(二之丸石垣の麓は内堀)で囲まれ、北御門と東御門が設けられていました。江戸中期には藩主御殿が二之丸から移され、藩政の中心となったほか、重臣の屋敷も建てられましたが、明治には陸軍の管轄となり、現在は城山公園(堀之内地区)として整備されています。
まず東御門を起点に外堀をたどってみましょう。東御門は失われているものの、櫓台と石垣は一部遺されています。外堀南東隅から振り返ると、外堀越しに天守群と本丸の櫓群が見えます。麓から天守を仰ぎ見ることができる城下町っていいなぁ。「松山や秋より高き天主閣」正岡子規の句が思い出されます(初夏ですが)。白鳥が泳ぐ外堀を眺めつつ南辺から南西隅で折れて西辺をたどり北西隅へ。北西隅には札の辻があったようで石碑が立てられていました。北辺の外堀は北御門跡までで、その先は埋め立てられています。
北御門跡から三之丸に入り、今度は土塁の上を歩きます。土塁上から見下ろすと外堀の水面までなかなかの高さ(約5m)があります。市民の格好の散歩道なのか、午前6時前後ながら土塁上で幾人もの人とすれ違いました。さすがは松山城。そして土塁上をたどって東御門に戻りました。
城山公園(堀之内地区)の北半分は令和9年完成予定で整備工事中でしたが、案内看板によれば、北御門の立体・平面表示や北御門東側の土塁の立体表示、武家屋敷の間取りの平面表示など、発掘調査の成果に基づきかつての姿を感じられるように整備されるようなので、完成後にぜひまた訪れたいものです。
…ということで、見事な高石垣といい、見応えある天守群といい、カメラ破損の傷心を癒してくれた登り石垣といい、さすが日本三大平山城に数えられるに相応しい素晴らしい名城でした。搦手側にも二之丸にも行けませんでしたし(ついでに100名城スタンプも押し忘れ)、整備後の三之丸も見てみたいので再訪はもちろんですが、次回は「?」の付かない「とことん松山城」でめぐってみたいものです。
> しんちゃんさん
カメラ破損のお見舞いありがとうございます。…といっても4か月遅れの投稿なので、いつぞやのカメラ派?スマホ派?の頃の話なんですけどね。保証期間はとうに過ぎていましたが、修理対応期間内だったためレンズ部分を交換して復活し、今も元気に活躍してくれています。それにしても、カメラを破損した時は城めぐりを続ける気力を失うほどに凹みましたが、登り石垣ひとつで気力を回復させるあたり、それ相応には城キチなんでしょうなぁ(笑)
+ 続きを読む
♥ いいね
16人が「いいね」しています。
加藤嘉明が築城を開始し、松平氏の時代になって完成。勝山山上を削平し三重三階地下一階の層塔型天守を築き、小天守と隅櫓などと連立式天守を構成している。高石垣を何度も屈折させ、その上に敵を迎撃するための太鼓櫓を設けるなど、高い防御性を誇る。
「松山城の魅力の再発見」をテーマに、アーティストやアート芸人たちが松山城をモチーフにしたアート作品を一挙展示。絵画から立体作品まで様々なジャンルや技法で表現された作品が並び、アートを通して松山城の新たな一面を楽しむことができます。会場内に点在するスタンプスポットを巡る重ね押しスタンプラリーも実施。開催日時:12月6日(土)~2026年3月8日(日)9:00~16:30(2月・3月は~17:00) 入場料:天守観覧料400円、二之丸史跡庭園入園料200円
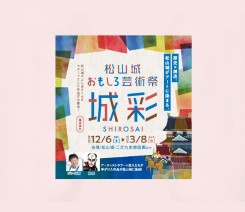
※ 内容は変更となる可能性があります、予めご了承くださいませ。
| 城地種類 | 連郭式平山城 |
|---|---|
| 築城年代 | 慶長7年(1602) |
| 築城者 | 加藤嘉明 |
| 主要城主 | 加藤氏、松平(久松)氏 |
| 文化財史跡区分 | 国重要文化財(大天守、野原櫓・乾櫓・隠門続櫓等櫓6棟、戸無門・隠門・紫竹門・一ノ門等門7棟、筋鉄門東塀等塀7棟)、国史跡(松山城跡) |
| 近年の主な復元・整備 | 松平勝善 |
| 天守の現況・形態 | 型式不明[5重?/1602年頃築・1642年改/焼失(落雷)]、連立式層塔型[3重3階地下1階/1854年再/現存] |
| 主な関連施設 | 小天守、北隅櫓、十間廊下、南隅櫓、太鼓櫓、筒井門、太鼓門、乾門、艮門東続櫓等、石碑、説明板 |
| 主な遺構 | 曲輪、天守、櫓、門、塀、井戸、石垣、土塁、横堀 |
| 住所 | 愛媛県松山市丸の内 |
|---|---|
| 問い合わせ先 | 松山市観光産業振興課 |
| 問い合わせ先電話番号 | 089-948-6556 |