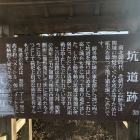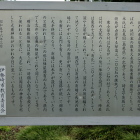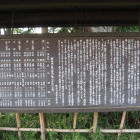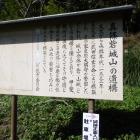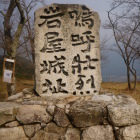赤木城から紀和鉱山資料館にスタンプをもらいに行く途中、ちょっと寄り道して丸山千枚田へ。
冬期は時季外れでしょうから、とりあえず行ってみる程度でさほど期待してなかったのですが…いや、これは凄いです。野面積みの石積みにより設けられた棚田が高低差160mに渡って段々状に連なっており、中央部には巨岩まで。棚田としての見応えだけでなく、城好きの心に訴えかけるものがきっとあると思います。
わざわざ来るのはなかなか大変ですが、赤木城に来られたのならついでにぜひ。私も、今度はもっといい季節(棚田に水を張ってから収穫までの間)に来たいと思っています。
+ 続きを読む