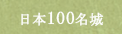毎年のように訪れている小諸城でずっと攻めあぐねていた信州蕎麦の「草笛」さん。
今回こそはと気合を入れて早めに出立し、開店40分前に着到。既に10人くらい並んでおられましたが、無事第1ターンで入店することができました🙌
当初の狙いはくるみ蕎麦でしたがメニューを見て蕎麦定食を注文しました。とってもおいしかったです!ごちそうさまでした😋
お腹いっぱいになったところで懐古園へ。
以前から、三の門だけでなく、北側(鹿嶋神社の方)からも入れるのでは⁉︎と気になっていたので確かめに行ってみました。すると、ありました!穴城を感じるアプローチに、天然の要害であったことがダイレクトに伝わってくる深い堀。感動しかないです🥹次からも多分こちらから入ると思います。(入園料は帰りに正面入口で支払います。)
水の手展望台で当時の不明門を想像。嗚呼絶景哉。
城内を散策していると、桜の馬場の案内板に「千曲川まで往復30分」とありました。千曲川が私を呼んでいる!もう、行かずにはいられません。ナマ足サンダルで蚊の襲撃に遭ったりもしましたが、途中に四阿もあり、“小諸城でこんな体験するとは思わなかった”なハイキングとなりました。
先ほど展望台から遠くに見下ろした千曲川。西浦ダムまで下り、振り返って見上げた山容に、お城って“部分”ではなくて“全体”なんだなぁと教えられた思いでした。
同じ道を戻って、ようやく見覚えのある天守台や石垣に出ました。
ひとまわりして最後に大手門へ。(この日は開館日でした。)
2時間半かけて城内を上ったり下ったりぐるぐるとまわった後だったので、展示資料の説明図が自分の足跡と重なってよく理解でき、それがとてもおもしろく、またうれしかったです。
小諸駅周辺は訪れるたびにどんどんすてきになっています。駅前のビルがなくなって、大手門がよく見えたのがびっくりでした。もう、“大手門見逃した!”なんてことは1,000パーセントないのではないかと思います。
充分に楽しんだところで、帰りは、“HIGH RAIL1375”で小淵沢へ。小海線、大好きです!
+ 続きを読む