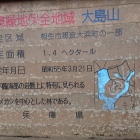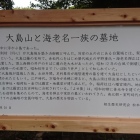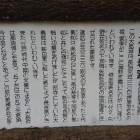JR福島駅から徒歩約15分くらい、阿武隈川沿いにある福島県庁が福島城跡になります。
上杉家が支配していた頃には水原親憲や本城繁長という曲者ではあるものの名将が詰めいてたという重要拠点になります。
対伊達と言う事で、それだけの武将が睨みをきかせる必要があったんですね。
県庁から延びる道には大手門跡碑が立ち、県庁入口には大きな解説と石碑があります。
遺構は開発によってほぼ消失してしまってます(県庁が建つくらいですからね(汗))が、県庁の脇にある紅葉山公園一帯が二ノ丸御外庭として再建されており、そこには出土された宝塔も置かれてます。
江戸時代初期には福島は幕府直轄地でしたが、後に初代福島藩主として本多氏が、その後堀田氏、板倉氏と徳川譜代が入れ替わり藩主になり、そのまま廃藩置県を迎えます。
最後の藩主・板倉氏を祀って福島城跡には板倉神社が建てられておりますが、そこからの阿武隈川の絶景は見逃せません。
ちなみにここから福島駅に向かう途中にある到岸寺には、福島城縁の史跡が数残されておりました。
福島は山形方面と宮城方面へ向かう際の拠点となる場所なので、行軍のついでにでも立ち寄られると良いでしょう。
+ 続きを読む