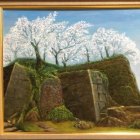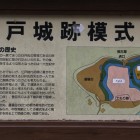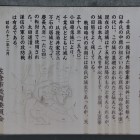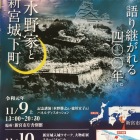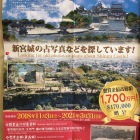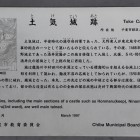現在は本丸跡は、鹿児島県歴史資料センター黎明館となっています。
所在地: 鹿児島県鹿児島市城山町7番2号
開館時間: 9:00~18:00(入館は17:30まで)
定休日: 月曜日(祝祭日の場合は翌日),25日(土日、祝祭日の場合は開館),12/31~1/2
入館料(常設展示): 一般 300円,高校・大学生 190円,小・中学生 120円
駐車場は無料でしたが、受付でスタンプを押してもらう必要がありました。
また、日本百名城のスタンプも受付で押すことが出来ます。
城山へ登って、20分ほどで展望台に到着
照國神社→島津久光像→二の丸跡(西郷隆盛像→鹿児島市立美術館→鹿児島県立図書館)→本丸跡(黎明館)と歩いてまわりました。
+ 続きを読む