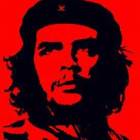3年前ですが、SL山口号に乗り秋の津和野城に行ってきました。
「新山口駅」からSL(C57)に乗り出発、汽笛の音を楽しみながらのんびり揺られて2時間、「津和野駅」に到着します(写真⑧⑨)。降りると駅前には動かないSL(D51)が展示されていました(写真⑩)。津和野城下は、きれいでとても落ち着いたたたずまいの街でした。白壁と水路に鯉が泳ぐ街並みを鑑賞しながら30分程歩くと太鼓谷稲荷神社(亀井氏が守り神として建立した神社)があります。その赤い鳥居の中をくぐりながらさらに10分歩くと登城用のリフト(兼スタンプ場所)に着きます(写真①②③)。そしてリフトの上からは本丸まで20分程です。リフトから先は誰にも会いませんでした。紅葉と城と城下の景色を一人占め! とても気持ちよかったです😊(写真⑤⑥⑦)。
津和野城は、鎌倉時代より吉見氏の居城でしたが、1601年に関ケ原の恩賞で坂崎直盛が3万石で入り三重の天主と石垣や櫓などを整えました。そして直盛は大坂夏の陣(1615年)の恩賞で4万3千石に加増。しかしこの翌年、ある事件で坂崎家は改易されたため、その後(1617年)に入った亀井氏は麓に館を移し、幕末まで亀井氏の居城となり、現在の美しい城下町が形成されたと伝わっています。
------------------------------------
余談:【坂崎直盛と千姫事件】
彼は本当にストーカーだったのか?
坂崎直盛(出羽守成正)と言えば🤔?
そうです! 大坂夏の陣で千姫を大坂城から助け出したあの人物です!
1615(元和元)年、大坂夏の陣で燃え落ちる大坂城を見た徳川家康は、豊臣秀頼は滅ぼしたいが、かわいい孫の千姫は何としてでも助けたい。よって「千姫を助けた者には嫁に与える」と思わず言ってしまいます。よって果敢に大坂城へ飛び込み、顔にやけどを負いながら千姫を助け出し家康の元へ届けたのが坂崎直盛でした。家康は大変喜び、直盛には褒美として津和野を4万2千石に加増しました。
でも最悪なのは、直盛はその時に千姫に一目惚れしてしまった事です。津和野城を改修しながら、千姫と夫婦になりここで暮らせる日々を夢見ていました。ところがいつまでたっても千姫はやって来ません。それどころか、千姫は姫路城主「本多忠政」の嫡男「忠刻(ただとき)」に一目ぼれ。父の徳川秀忠は二人の結婚を許します。(姫路城の西の丸に長局や化粧櫓がこの時に作られたのは有名ですよね!😊) 直盛は話が違うと秀忠に直談判。しかし取り合ってもらえません。直盛はあきらめられず、夜な夜な千姫の屋敷へ(これって今で言うストーカー?) でも門前払い(😱~)。千姫にとって直盛は好みのタイプではなかったようです(助け出した時の顔のやけどで醜かったとか・・・無骨な直盛より忠刻のようなイケメンタイプが好きだったとか・・・)。ならば強硬手段! 忠刻への嫁入り行列を襲撃し千姫を強奪してやろうと計画。しかし、これを知った秀忠は超激怒! 直盛に切腹を命じましたが、愛想を尽かされた家臣から切られたそうです(柳生宗矩に斬られたという説もあります)。
私は津和野城の最も高い三十間台石垣の上に立ち城下を眺めて見ました(写真⑤⑥⑦)。彼は、この景色を千姫と一緒に見ながら幸せに暮らせる日々を、ただ純粋に夢見ていただけなのではないでしょうか?
以上、哀れな男の物語でした😩。
+ 続きを読む