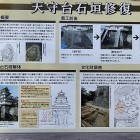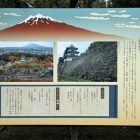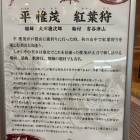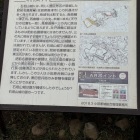【母坪城(穂壺城)】兵庫県丹波市柏原町
<駐車場他>駐車場はなし。登城口に歩道に掛かるが1台停めれる。ストック要。
<交通手段>車
<見所>2重堀切・竪堀
<感想>丹波の黒枝豆購入旅。久しぶりの攻め城と投稿でご無沙汰です。恒例の黒枝豆の収穫時期なので購入がてら城攻略をしました。朝に丹波篠山市の鍔市自然公園にて湧水を汲んで、黒枝豆を購入、JAひかみに行きました。丹波市・丹波篠山市の城びと登録城はほぼ攻略してしまっているので、城びと未登録で遺構の良さそうな母坪城を選んで攻略しました。
母坪城の築城年代は定かではないようで、南北朝時代に仁木氏の高見城の支城として築かれたようです。戦国時代、細川晴元の家臣赤沢景盛が城主の時に波多野氏に攻められ落城したそうです。その後は稲継壱岐守という者が城主であったそうですが、1579年に明智光秀によって攻められ落城しました。
城郭は独立丘陵の山城で、北側が柏原川・加古川が流れていて後ろ堅固となっています。城跡の南西端は急崖で大手は南東端になるようですが柵があって行けませんでした。
登城口は北側の尾根終わりの<35.152657,135.040921>にあります。城郭構造は主郭を中心に南北に連なる連郭式で主郭から北側は3段舌状曲輪が連なってその北に見事な2重堀切があります。2重堀切の北側にも3段程の曲輪が連なります。主郭から南側は2段舌状曲輪があり、そこから高い切岸となっていてガクッと下がります。切岸は高低差があり見応えがあります。高切岸から南側の曲輪群は緩やかな広い段曲輪になっています。主要部入り口の兵を多く置く武者溜まりのような感じと見ました。残念ながら主郭は雑草で鬱蒼としていました。
とりわけ見応えがあるのは竪堀で、城跡東面に3条、南面に1条あります。東面の2条はハの字になっていて、ハの字の間に段曲輪が配されています。南側の竪堀が特徴的で、主要部から南北に山の稜線に沿って掘り込んでいます。一見切り通しみたいだけれども、主要部高切岸の手前でぷっつり切れているので、誘い込むようないい竪堀です。全部で4条ある竪堀も横幅が広く見応えがありました。西面は加古川が流れているので、竪堀は必要なかったと思われます。
戦国期の良好な遺構を残した見応えあるいい城跡でした。城びと登録していないのが不思議。
<満足度>◆◆◇
+ 続きを読む