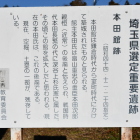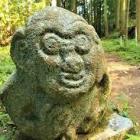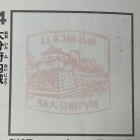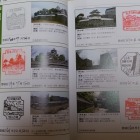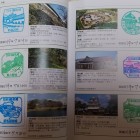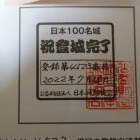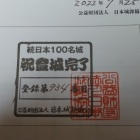南北朝期より丹生川上神社神主として東吉野地方を治めた小川氏が戦国期に築いた城で、高見川に三方を囲まれたハルトヤ山の南北にのびる尾根に連郭式に曲輪が並んだ山城です。筒井順慶が大和国の支配を広げる中、小川氏は没落し、小川城も廃城となったと思われます。
北麓の東吉野村役場から駐在所の裏手を通って登城開始。登城道は稲荷社の参道(ドコモ通信施設の整備道)として樹脂製の階段が設けられていて、墓地を抜け鳥居をくぐって20分弱で北端の堀切に到着。ここからが城域です。
北端の堀切は土橋の両側ではずいぶん浅くなっていますが、東側に長く続いて竪堀となって東斜面に落ちています。堀切の先に広がる北の曲輪は東西二段になっていて、西側上段には通信施設が設置されています。通信施設の南にも堀切と土橋があり、土橋を渡ると二の曲輪です。二の曲輪も東西二段で、東側下段からは東麓に至るであろう登城道が続いていました。二の曲輪の南にも堀切があり、西側はほとんど埋まっていますが、東側は竪堀となって続いています。また、竪堀の脇には石組みの井戸跡も見られます。二の曲輪南の堀切の南側には石積み(たぶん後世のもの)があり、石積みの上が主郭です。主郭は南北に細長く、北側に稲荷社の社殿が建てられ、南端の土壇には石垣(これもたぶん後世のもの)が積まれ、小川城址の石碑が建てられています。土壇の背後は二重の堀切で南に続く尾根筋を断ち切っていました。
尾根上の曲輪群を五条の堀切で区画しただけの単純な縄張ですが、浅くなっていたりはするものの遺構はしっかり遺っており、いかにも中世山城という感じで、これはこれで充分に満足できる城でした。
+ 続きを読む