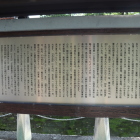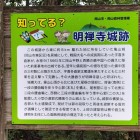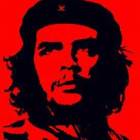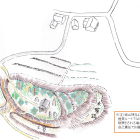兵庫県神戸市にある五色塚古墳は古墳が作られた
当時の姿が見られる野外博物館として、1965年から
10年の歳月をかけて発掘調査と復元整備が行われました。
全長194m、後円部の高さ18.8mで兵庫県では最大の
前方後円墳です。建造は4世紀後半ごろと見られ
周囲を鰭付(ひれつき)円筒埴輪や鰭付顔型埴輪で
飾り立てています。
とにかく眺望がすばらしく、明石海峡や明石海峡大橋が良く見えます。
淡路島も良く見え、テンションが上がります。
近くに舞子台場もありますので、その前に訪問してみては
いかがでしょうか?この地域にしては珍しく
立派な駐車場がありますよ。
五色塚古墳 専用駐車場
兵庫県神戸市垂水区五色山4丁目12
+ 続きを読む