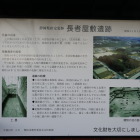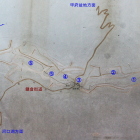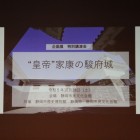水の手郭現地見学会に行ってきました。水の手郭は天守曲輪の北側中腹に位置し、連立天守群の台所にある穴蔵に設けられた埋門から水の手門を抜けてZ字に曲がった道を下った先にありますが、穴蔵から先は普段は立入禁止なので、こういう機会をずっと待っていました。
わかやま歴史館前に集合し受付で資料をもらうと、事前説明の上、水の手郭に出発。集合場所からは多聞櫓の下に埋門の上端がわずかに見え、埋門の右下方だからあのあたりかな…と考えるとわくわくしてきます。水の手郭には埋門を抜けて行くのかと思いきや、新裏坂の途中から立入禁止のロープを越えて、刻印の多い浅野期の石垣や鶴の渓の石垣の上を進みます。普段見上げている石垣の上に立つと、遥か下方に鶴の渓が見渡せます。相当な高さです。天守曲輪の北側に回り込むと目前に水の手郭の石垣が見えてきました。後世のものでしょうか石垣には絵図にない入口が設けられていますが、北西隅部は水の手櫓の櫓台と思われます。
石垣の入口から水の手郭に入ると、資料を参照しつつ学芸員さんから説明を受けました。平成30年7月のいわゆる西日本豪雨で水の手郭の石垣や通路が崩落し、復旧に2年あまりを要したこと、谷地形ならではの水の手郭だが、そのために山上の雨水が集中して流れ込み土砂崩落が生じたと考えられること、水の手郭の石垣は緑泥片岩の野面積みであり、豊臣・桑山期の古い石垣と考えられてきたが、復旧工事に伴う発掘調査で石垣の裏込層上部から江戸前期の瓦や江戸後期の磁器が出土しており、江戸期に何度か積み直されているのが判明したこと、復旧工事では崩落前の石垣の写真と見比べて石材の位置を特定し、なるべく元の位置に戻すよう積み直したが、江戸期の石工は元の位置に戻す必要はなかったので、現代の石工のほうが大変な作業を求められている…などなど、興味深い話を伺うことができました。
説明に続いては、しばし自由に水の手郭を散策。黄金水と呼ばれる井戸跡があり(コンクリートで囲まれていますが)、復旧した石垣の左下にも野面積みの石垣が見られ、緑泥片岩の岩山だけあって岩盤むき出しの箇所もありました。
散策の後は来た道を戻るのかと思っていたら、Z字状の通路を上がって埋門も見学できるとのこと。石垣沿いの通路を上がり二度目に折れるあたりで振り返ると、木々の間に先ほどまでいた水の手郭が覗いています。さらに上がって水の手門の石垣を過ぎ、埋門へ。石段の上の埋門をくぐると岩盤を削り込み緑泥片岩を積んだ穴蔵になっています。いつもは台所から穴蔵を覗き込むことしかできないため、穴蔵から台所を見上げることができるのは貴重な機会ですね。
さて、これで水の手郭から埋門までを見て回ることができましたが、せっかく立入禁止の天守曲輪北側に来ているのだから、普段は見られない北側からの天守群を堪能したいと思います(続く)。
+ 続きを読む