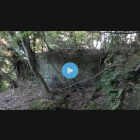【神戸城】
<駐車場他>神戸公園駐車場無料18台程度
<交通手段>車
<見所>天守台・現存移築櫓・現存移築大手門
<感想>神戸城は天文年間(1532ー1555年)に神戸具盛が築城しました。織田信長の3男信孝を神戸氏に養子入れした後に改修を施しました。その時に天守が築かれたようです。天守櫓は文禄年間に桑名城に移築されましたが城は2万石の神戸藩として修築されながら明治まで残りました。
四日市のにある顕正寺の移築大手門→鈴鹿市蓮花寺にある移築二の丸太鼓櫓を巡り城跡にきました。城跡は本丸の大半と天守台、本丸の西側の堀が残されています。二の丸は神戸高校に本丸周辺は公園化しています。
天守部分は天正時代に神戸信孝が築いたものであるようで、残された天守台は隅角部は算木積み未発達で丸みのある石を使用しています。河原石かとも思われます。南面に鏡石があり、石段前に立石が置いてあります。なんといっても良いのが憶測ですが信長監修かもしれないのがたまらないですねえ。暫く天守台にて浸りました。大満足です。
<満足度>◆◆◆
+ 続きを読む