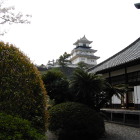初・中尊寺金色堂をしっかりと目に焼きつけ、つぎに目指したのが接待館です。地図上では衣川をはさんですぐですが、近道はなさそうなので参道を戻り、通り沿いを進みました。
橋を渡ってからは土手の上を、途中にあった階段を下りてしばらく歩いて到着しました。
堤防工事に伴う発掘調査により12世紀の大規模な遺跡であることが判明、堤防のルートを変更して国史跡として保存されることになったという経緯をもつ遺跡は衣川の浸食により失われた部分も多いようですが、大量に発掘されたかわらけからまさに接待のための場所だったと判明したのだそうです。(奥州市教育委員会作成パンフレット、PDFファイルあります。)
現地には長大な堀跡のほか貴重な土塁跡が細長い林となって残っていました。この林は衣の関道から見ると「奇跡の土塁」感がハンパなかったです。
+ 続きを読む