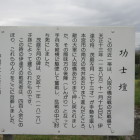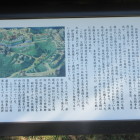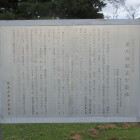伊勢崎市境町関連のHPを見ると、岩松氏の陣僧・松蔭が残した文献[松蔭私語]の内容に多く拠るらしい。岩松明純(岩松家純の子)が拠った城である。文明9年(1477)長尾景春の乱の際、山内上杉勢の籠もる五十子陣は景春の軍勢に包囲され陣を撤退する。岩松明純は上杉勢として戦うが、金山城に退く時に一時武士城に入る。利根川を挟んだ南5㎞ほどに五十子陣はあり、乱の際に取り立てられた陣城であったものといわれる。北条氏時代は金山城主由良氏の家臣根岸三河守の居城だったが、豊臣秀吉の北条攻めにより、金山城は落城し武士城も廃城となる。保育所の西にある堀は堀跡で、元は北に延びており、水遊びや魚捕りをしたらしい。今も御嶽山の東に[舛形]という小字名が名残りである、と記されている。
広瀬川と粕川の合流点にある高台。地元では御嶽山(オンタケサン)と呼ばれているらしい。福祉センター・特養ホームの間に、境御嶽山自然の森公園の駐車場が設けられている。公園内は2段程の段差があり、郭として機能していたのだろうか。遺構と分かる明確なものは見当たらない。南の斜面に虎口跡を思わせる地形があるが不明。保育所の西に堀跡・・云々とあったが、訪問時情報が無く確認していない。訪問時園内はほぼ全域に曼珠沙華が咲いており、見学者が多く散策していた。
+ 続きを読む