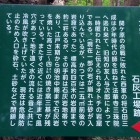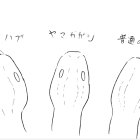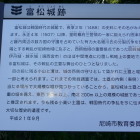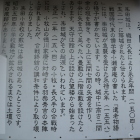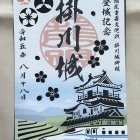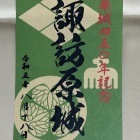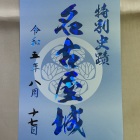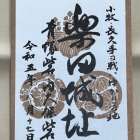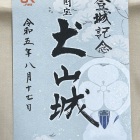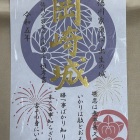(23人目)「石田三成」の続きです。
秀吉に仕え出世への始まりとなった「長浜城」を訪れてきました。
15才で家臣となった佐吉は、ここで秀吉に小姓として仕え、得意の算術で才能を発揮し徐々に頭角を現します。そして8年後、秀吉の中国攻めの時に初めて従軍し、それから賤ケ岳、小牧長久手の戦いを通じて、この長浜から出世への道が始まりました。その後、九州征伐、小田原北条攻めなどで、兵站の才を存分に発揮します。しかし唯一戦った忍城では失敗してしまいました(笑)。そして奥州仕置を経て、朝鮮出兵のため名護屋城へ。
私は長浜城の天守に立ち、琵琶湖を眺めてみました。南側には彦根城や佐和山が見えました(写真④)。また北側には賤ケ岳(写真⑤)や小谷城(写真⑥)、東側には伊吹山が見えました(写真⑦)。
佐吉(三成)は、ここで秀吉に仕えながら、いったいどんな夢を見ていたのでしょうか?
【余談1】大蛇(おとち)の岩窟
伊吹山中を敗走しながら秀吉と出会った観音寺を目指した三成ですが、追手が迫ってきたため、今度は母の墓がある法華寺を目指します。そこで地元の人々に助けられその法華寺の山中奥にある「大蛇の岩窟」に匿われました。本当は、長浜からその岩窟まで行こうと思っていたのですが、とんでもない山中みたいで(だから隠れるのに最適だったのかも?)、熊や蜂や蛇が出て道にも迷ったりもするとの事、一人で行くのは大変危険な場所のようなので、心残りではありましたが断念する事にしました。いったいどんな場所だったのでしょうか? 長浜市のHPにボランティアガイドが行った時のツアー写真がありましたので代わりに掲載させていただきます(写真⑧⑨)。行く時は個人でなくボランティアガイドと大人数のツアーで行かれた方がいいようです。またここでの美しい秘話は以前私の(12人目:田中吉政)でお伝えしましたのでよければまた参照して下さい。三成がそこで食べたニラ粥はいったいどんな味だったのでしょうか?🤔
【余談2】にしんそばと地ビール
長浜駅前で名物「にしんそば」と「地ビール」で昼食をとりました。猛暑の中を歩いたのでとても美味しかったです。三成にもこの「伊吹バイツエン」飲ませてあげたかったな~😊(写真⑩)。
次は、三成の人生ターニングポイントになった(肥前名護屋城)を訪れます。
+ 続きを読む