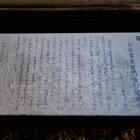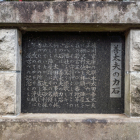大規模な山城で曲輪が連なり至る所で見事な石垣を見ることができ、素晴らしかったです。
中世山城で、これだけの石垣を築いた六角氏の権力や技術は凄かったと思います。
観音寺城は3回目ですが、個人的に今回のお目当ては、後藤邸・進藤邸、大石垣、御屋形跡でした。
観音正寺南西下の後藤邸・進藤邸は、竹林が伐採中で立派な石垣を見ることができました。
通路が寺院の参道のようでもあり、曲輪の配置が寺坊跡を利用したようにも見えました。
大量の竹を伐採して下さっている方々に感謝です。
池田丸南下の大石垣は、以前行った時は木があり間近でしか見えませんでしたが、伐採され石垣の全容が見え、山上では最も立派な高石垣でした。
ただ、石垣の崩落が進んでいるようですので、対策を願いたいです。
山麓の御屋形跡に初めて行きましたが、六角氏の居館とされるだけあって、観音寺城で1番高い位の石垣で見応えがありました。
+ 続きを読む