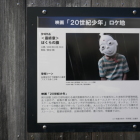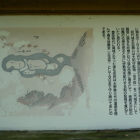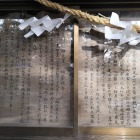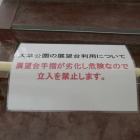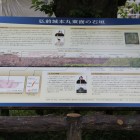愛知県の焼き物の二大産地といえばご存じ常滑市と瀬戸市です。常滑焼は一時期、瀬戸焼に押され江戸時代前期まで勢いが衰えたのですが、尾張藩の支配下で勢いを取り戻しました。650~100万年前に存在した東海湖の底に堆積した鉄分を多く含む良質な粘土を使用しており、大きな壺や甕を製作するのに適していたようです。江戸時代後期(天保年間)に連房式登窯が導入され、効率よく土管、甕、朱泥茶器などを生産できるようになりました。瀬戸物と同じく猿投窯の系譜とされ、釉薬を用いない「焼締」による焼き物が特徴です。
また六古窯の一つに数えられ、日本遺産になっています。
土管坂は常滑市を代表する観光地「やきもの散歩道」の中にあります。海外でも有名らしく台湾人とみられる観光客が「タ~イワン」と言いながら記念写真を撮っていました。壁を覆い尽くしているのは明治時代の土管と昭和初期の焼酎瓶で坂道には「ケサワ」と呼ばれる土管の焼成時に使用した捨て輪の廃材(焼台)が敷き詰められ、滑り止めになっています。
写真のでかい招き猫は とこなめ見守り猫「とこにゃん」です。幅6.3mあり、日本一巨大と言われています。とこなめ招き猫通りの南側、陸橋の脇に据えられ、やきもの散歩道の入り口で観光客を出迎えてくれます。
+ 続きを読む