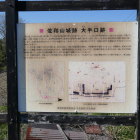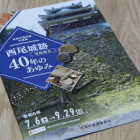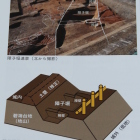ヲンネモトチャシから100kmを遥かに超える道のりを運転して到達。標津遺跡群伊茶仁カリカリウス遺跡の中にあるチャシです。有料区域の中にありますが、330円を支払う価値はあります。零汰さんも投稿されている通り、湿原をはじめとして見どころがたくさんありますから。肝腎のチャシは、いただいた案内地図では円弧を描く遊歩道の外側のテラス、近くの案内板では遊歩道の内側にある「村長さんの家?」のくぼみになっています。とりあえず両方の写真を投稿しておきました。標津遺跡群伊茶仁カリカリウス遺跡は日本遺産「鮭の聖地」の構成資産になっています。ここに来る前に郷土料理の店で三代漬け丼を昼食としていただいたのはベストチョイスだったと思います。
+ 続きを読む