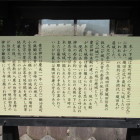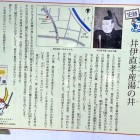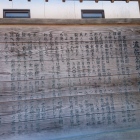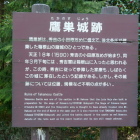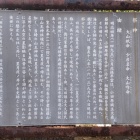こちらの城跡は遺構を見ながら絶景を味わえる所です。こちらは主郭部は山頂に有り、南に0.5km北に2.4km、合計3kmに渡り稜線に沿って11か所の城館を配置する城跡です。味見峠の登山口から主郭部に辿り着く間にも、砦と表示されてたり、小高い山があるのですがここら4か所が城館跡らしく遺構も残っているようです。当時の自分はそんな知識も情報も無く、絶景に打ちのめされて目的である遺構を探す事を忘れてしまう程でした。
主郭部は南北に約300m程有り、片方からこれ程の範囲の城跡全域を見渡せる城跡は中々無いのではないでしょうか。通常は山の上で樹木に覆われた中を散策して全体像は縄張り図でしか把握できないです。九州で樹木が無く主郭部全体が把握できる城跡は、福岡の鷹取山城、大分の伐採山城、佐賀の隣り合わせの2つの城の基肄城・木山城が思い付きますがその中でもこちらの城跡は高低差があり見渡し易くお勧めです。これも地域の方々が保存に尽力されているからの賜物なでしょう。
が、遺構に関して主郭部は少々少な目。大きい堀切と各曲輪の土塁位です。南に下がると堀切が2か所、その先に2つの城館跡が有るようですが軽い気持ちでは見る事が出来ないのではないでしょうか。
写真7は登山道でとても登りがキツイ場所です。訪問した日にこの坂道の先で地元の保育園?幼稚園?の園長と保母さんが草刈をしていました。話をした所遠足でこちらの城跡に登るんだとか。「あの坂道を、小さな子供が。」この話を聞くとこの城跡が確実に地域と密着している事が分かります。
+ 続きを読む