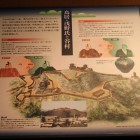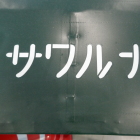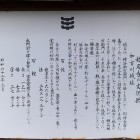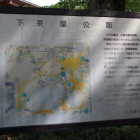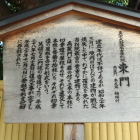とある煩悩の登城目録さんのアクセス方法を参考にさせていただきました。東横線で菊名駅へ。東口を出たところに,臨港バスのバス停があります。鶴見駅西口行きのバスに乗り,馬場谷バス停下車。バス停からは予想以上に傾斜があったため,キャリーバッグ持ちにはキツかったです。帰りに気がついたのですが,近くのローソン裏からショートカットできます。バスはかなりの本数があったので,あまり時間は気にしなくていいと思います。
竪堀は推測ですが,たぶん間違いないと思います。
横浜土産は毎回悩みどころですが,70周年のロゴが見えたので「横濱ハーバー」で。期間限定の,抹茶黒蜜味は美味でした。
+ 続きを読む