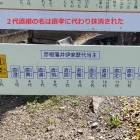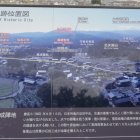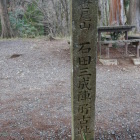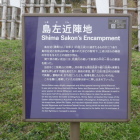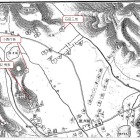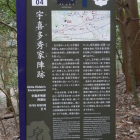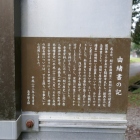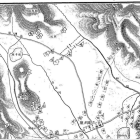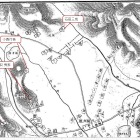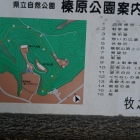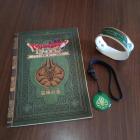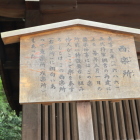トクさんの関ヶ原の投稿、いつも楽しみに読ませていただいております。関ヶ原に関しては諸説があり、昨今学会で次々と新説が発表されております。私も関ヶ原を踏まえたうえで会津等に関わる次の投稿に繋げていきたいと考えており、従来とは異なったスタンスでの投稿になりますが、お気を悪くせずご了承いただければと思います。私なりに旧説を踏まえながら、新説も考慮して散策をする方式を取っており、近代関ヶ原研究の祖・神谷道一翁には特に敬意を表しております。
さて蒔田城の投稿になりますが、ここからいつものグダグダ投稿に戻ります。蒔田城は吉良氏の居城とされ、横浜英和学院が城址にあたります。と、言うわけで下校の時刻とも重なったため、とても写真を撮ったりできる状況ではありません。確実に通報されます。逃げるように裏手に走っていくと道がとたんに狭くなり戻って来るのに難儀しました。
そんなわけで写真が少ないため、今日の昼食で作った「水攻め」カレーをついでに載せます。郭のすみっこに乗っているソーセージは櫓をイメージしてます。さしずめ対岸にいる人影二つ(?)は豊臣秀吉と石田三成といったところでしょうか。
+ 続きを読む