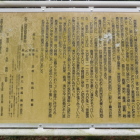2度目の登城-2/8 東曲輪編の続きです。
本曲輪の大手口に当たる東虎口から入城し、気に成っていた北東の突出し櫓台?に登り周辺を眺める、東曲輪も一望できる、北堀、東堀を上から眺める事が出来景観抜群のポイント、本曲輪も南西に向かって一望できる、北土塁上を西に北虎口、土橋を上から眺める、降りて北虎口は子供達が家族を含めて北土塁の芝滑りで賑わっていましたので、パスして中央南北の道を南へ、復元建物東屋、西側を建物域と西池、石敷部とに分けてる東西の低い土塁を観ながら南西虎口へ、南土塁上から復元された南西馬出が一望できる。
南西虎口を通り、階段、木橋を渡って南西馬出に入る、東に土橋、その東の田畑は整備予定地?で草刈されて整備されてる、西には木橋で曲輪Ⅴに繋がるがまだ整備予定地、木橋の脇に古い小田城跡の案内板が立っている。南西馬出の西、南、東には低い土塁が巡って居り土塁上には低い灌木が植栽されている、北側は開放されています、馬出の周囲は堀が廻って居る、よく整備されて居ります。
2度目の登城-4/8 本曲輪虎口編に続く。
+ 続きを読む