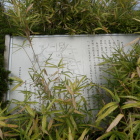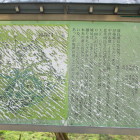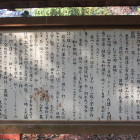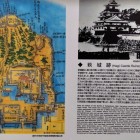説明板・案内は見当たらなかった。星神社の鳥居のはす向かいに台地に上がる道がある。如何にも虎口風な風景だが、単に車で畑地に行く為のものかも知れない。城跡は驚く程の広さがあるが、耕作地が一面に広がっている。区画されたような遺構は分からない。先人さんの情報に東と西側に土塁跡が見られるようで、近くに寄ってみたところ、高くはなく篠など植物が生い茂り判断がしづらい。周辺の台地の端はこんもりと植物が高い場所が多く、全て土塁跡かと見てしまう。遺構ではないが、星神社の社殿が建つ辺りの方が余程城跡らしく見えてしまう。
+ 続きを読む