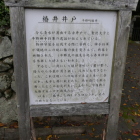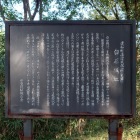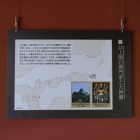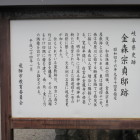池上曽根史跡公園は南北1.5km、東西0.6kmという全国でも屈指の弥生時代の環濠集落の跡地に造られた公園です。吉野ヶ里遺跡の外堀が2.5kmだから、それ以上になるのかな? かなりの規模ですね。
さすがに大阪の町中でそれだけ大規模な遺跡の再現は無理なので、大型高床式建物をはじめとした数棟の再現にとどまっていますが、古代のロマンを感じますね。ただの集落でなくて環濠というのが良いですね。城のご先祖様にあたるので、敬意をもって訪問します(どないやねん)。関西にかかわる投稿なのでカッコの中のツッコミの人もエセ関西人っぽくなっています。
ちなみに私、愛知在住ですが関西の血が半分流れています(和歌山系)。
+ 続きを読む