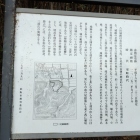北畠氏の本拠地である多気に通じる中村川流域を守る城の一つです。比高はないですが、重厚な土の作りで、また、城びと先人の指摘のように、縄張りにくふうがあり興味をひかれます。北側の登城口から少し登ると、比較的緩やかな傾斜で東側に向けて斜面を斜めに登らせます。この道はずっと郭から見降ろされているのですね。
ちとわけがあって、南側からアプローチしたのですが、南側からⅠ郭に入る、堀を渡る橋とその先の平虎口が「三重の山城 ベスト50を歩く」の縄張りに見られず、縄張りと現地が合わなくて、どこにいるのかしばしうろうろしてしまいました。
ぴーかるさん、滋賀県&鳥取県コンプリートをおめでとうございます。最近の投稿に「ラスト*城目」とありましたね。滋賀県のラストは打下城にされたのですね。打下城は湖西線から見えます。他にも湖西線から見える城がいくつかあります。コンプリートへのプレゼントに、今朝、湖西線から撮った山城の写真を貼り付けました(写真10枚目)。
+ 続きを読む