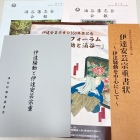名古屋地下鉄本山駅から歩いて数分と、広大な尾張平野に広がる名古屋市内の小高い丘に城跡はあるが、そこそこ遺構が残る。
当時しのぎを削っていた三河方面へも近く、深い空堀、土塁、切岸を駆使して守り堅固な城としたことがわかる。本丸周辺の空堀が見どころ。
信秀は北の斎藤道三と戦いながらも、拠点は勝幡城、那古野城、清洲城、古渡城、そして末森城と三河方面の領土確保、拡張に重点をおく。
信長は父に反してひたすら北上し上洛を目指す。今川義元を討ち果たしても松平元康と同盟して三河方面を任せたのはご承知の通り。信長は早くから天下布武を意識していたと思いたい。
+ 続きを読む