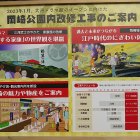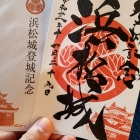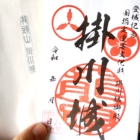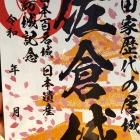とことん江戸城(牛込門)
(2022/06/24 訪問)
(続き)
市ヶ谷門から外堀石垣と思しき石材が点在する牛込濠沿いの土塁上を歩いて牛込門に到着。牛込門はJR飯田橋駅西口を出て左手すぐの交差点にあり、枡形の北隅と西隅の石垣が現存しています。東半分は道路になっていて石垣は失われていますが、富士見町教会前の歩道に枡形石垣の位置が舗装表示されています。道路の向こう側の枡形石垣とあわせて見れば、櫓門の位置も枡形の規模も体感することができ、素晴らしい史跡整備だと感心しました。また、富士見町教会前から発掘された「阿波守内」の銘のある石垣石が飯田橋駅前交番の西隣に移設されています。
飯田橋駅西口の駅前広場には江戸城外堀跡の解説コーナーがあり、様々な案内図や説明板、牛込濠と飯田濠を隔てる土橋に設けられた水位調整用の堰に用いられていた石が展示されています。また、総武線ホーム(堰が発掘された位置)でも堰の発掘調査の成果などが解説されているようです(未確認)。西口改札外コンコースにも枡形石垣や外堀土塁の説明パネルがあり、その奥には土塁が復元されているようですが、工事中のため確認できませんでした。さらに、西口駅舎2階には牛込門と外堀を望む史跡展望テラスがオープンしていますが、開館時間前のため2階には上がれませんでした…。それにしても、国史跡に指定されているにしても、四ツ谷駅(JR)、市ヶ谷駅(東京メトロ南北線)、飯田橋駅(JR)と、それぞれの駅構内外に外堀や門の解説コーナーが設けられているというのは、さすが江戸城といったところでしょうか。
牛込門の東隣、日本歯科大学と附属病院の間には旗本屋敷跡の説明板があり、附属病院の竣工までこの地にあった富永邸に由来する石碑が遺されています。旗本屋敷跡から坂を下って小石川門に向かいます(続く)。
+ 続きを読む