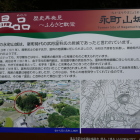岩村では古い街並みを観ることができます。NHK朝の連続テレビ小説「半分、青い。」のロケ地ともなりました。
以前から私が興味を持っている佐藤一斎は岩村藩家老の次男で、門下生には、佐久間象山、山田方谷、渡辺崋山などがおり、著書である「言志四録」は幕末の西郷隆盛などに大きな影響を与えたと言われています。彼の残した言葉が街の中に貼られていていました。
ここはカステーラが有名な街です。長崎から離れているこの地に、なぜカステーラなのか疑問に思っていました。長崎県に医学を学びに行った岩村藩の医師が医学とともにカステーラの製法を持ち帰り、この地で作られるようになったといわれています。今回は松浦軒本舗さんのカステーラをお土産に購入しました。
+ 続きを読む