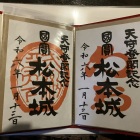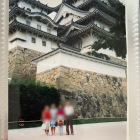※杉山城、鉢形城、忍城とともに登城
7:48新宿(JR)、7:54,8:00池袋(東武)、8:56武蔵嵐山 ※レンタサイクル:嵐山町ステーションナビ嵐なび
(1.0km)菅谷館(続百名城スタンプ 嵐山史跡の博物館9:00-16:00月休)
(2.8km)杉山城(続百名城スタンプ 嵐山町役場8:30-17:15)
※時間がある場合は嵐山渓谷に立寄りもいいかも
11:33武蔵嵐山、11:40,11:43小川町、11:56鉢形
(徒歩25分)鉢形歴史資料館(百名城スタンプ 9:00-16:00月休:閉館時駐車場正面入口) + 鉢形城跡
14:25鉢形歴史資料館前(休日:路線バス)、14:33,15:12寄居(秩父鉄道)、15:43,15:44熊谷、15:50持田
※平日は鉢形歴史資料館から徒歩30分で寄居駅へ
(徒歩16分)行田市郷土博物館(続百名城スタンプ 9:00-16:30) + 忍城散策
18:07持田(秩父鉄道)、18:14,18:21熊谷(JR)、19:30新宿
+ 続きを読む