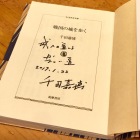新年初登城が 2月となってしまいました。全然お城行けませんでした。まあでも行けてよかったです。テストがもう近いので…
三雲城に行ってきました!三雲城は佐々木六角氏のお城だそうです。織田信長との戦いで負けたあとこの城に逃れたそうですが、その 2年後に落城しました。またアニメにもなった猿飛佐助がここで修行をしていたそうです。
三雲城は見るところが主に二つあり一つはもちろん城址なのですが、もう一つが落ちそうで落ちない岩です。まあいわゆるパワースポット。ここにはよく受験生が来てお参りをするそうです。
僕は今回三雲城を巨石群→城址の順に行きました。巨石群(落ちそうで落ちない岩)の投稿は後ほど
巨石群から馬の背道という道を通って城址に向かいました。馬の背道には土塁が残っています。(写真⑧)
馬の背道を通ると主郭北の石垣が高ーいところに見えます。(写真⑥)結構石が大きいですね。またこの城は採石場があったようで、今も石が転がっています。おそらく石垣の石は本城のものを使っているのでしょう。
階段を登っていくとこの城1番の見どころである枡形虎口が見えてきます。(写真①)虎口の石垣には石切矢穴列跡が残っています。(写真③④)近世前期の矢穴跡が見れるのはこの辺の城だそうです。
枡形虎口を通ると城郭Iに入ります。そこには井戸があり、穴太積の石垣でできています、山城で石垣造りの井戸を見たのは初めてです。(写真⑦)
また土塁も残っており(写真⑨)、その裏には竪堀群が見えるのですが、草だらけで全然見えませんでした泣。おそらく冬でも見られないのでこれは誰も見れないんじゃないんでしょうか?
さて次は城郭IIに行きます。 続く
評価★★★☆☆
100名城じゃないが、遺構の保存状態は素晴らしい。しかし、遺構の見ずらいところや道がはっきりしない場所もちらほらある。
+ 続きを読む