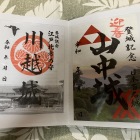今月のみ初公開している西小天守を見るために三連休を利用して姫路城へ。大天守はもちろん、イの渡櫓→東小天守→ロの渡櫓→乾小天守→ハの渡櫓→西小天守、と回ることができ、ニの渡櫓は西小天守から中を見るだけでしたが、そこから大天守への扉も見ることができました。連立式の天守、櫓をほぼぐるりと楽しめました。
西小天守からは水の五門内側枡形が良く見えるし、水の四門から水の五門への道もよく見えました。敵を上から攻撃で来たんでしょうね。
連立天守の内側エリアは思ったよりは狭く感じました。台所櫓があるせいかもしれません。
天守以外も官兵衛石垣や搦手門などお堀の周りも散策。いろんな顔があるのが姫路城ですね。
+ 続きを読む