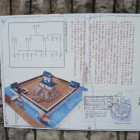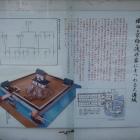打下城から自転車で5分くらいで、大溝城入口付近(35.293450、136.012477)に着きました。
1572年(元亀3年)織田信長が高島郡に進攻すると、1579年(天正7年)織田信澄(津田信澄)が高島郡を領し、明智光秀の縄張りで大溝城が築かれました。
1582年(天正10年)本能寺の変で信澄は明智光秀の娘を正室にしていたことから、大坂で殺害されてしまいます。
信澄の後には、丹羽長秀・加藤光泰・生駒親正・京極高次と目まぐるしく城主が替わりますが、京極高次が近江八幡へ転封となった後は無城主となったそうです。
1619年(元和5年)分部光信が伊勢国上野より20,000石で入封しましたが、元和の一国一城令の対象となり、三の丸を残して大溝城を破壊しました。
分部氏は三の丸に陣屋を構え、11代続き明治維新を迎えました。
天正前期と思われる野面積みの天守台が、崩れつつもしっかり残っています。
攻城時間は10分くらいでした。次の攻城先=大溝陣屋(城びと未登録 滋賀県高島市)に自転車で向かいました。
+ 続きを読む