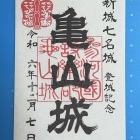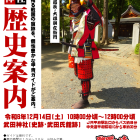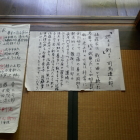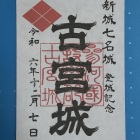もみじまつり前日-6/8 石垣長塁と諸門の1/2編の続きです。
3の丸表中門枡形を登りきると四足門跡で2の丸へ2の丸西エリアはもみじまつりの飾りつけ、楓のもみじ散策路、備中櫓の真下です、写真を沢山撮って、東方向へ切手門辺りの石垣群が構えてる、本丸長局石垣長塁が目を引く、切りて門枡形より備中櫓東面を見るビューポイントに当たる、本丸東側の石垣長塁の南端の14番門跡、包(鼓)櫓台が目に留まる、切りて門枡形を西に折れると本丸大手の表鉄門跡、登ると本丸、東側の雁木を備えた石垣長塁が目を引く、北に粟積櫓台、西に本丸曲輪、天守台、南出っ張りに復元備中櫓と目を引き付けるものばかりです。
今回搦手の裏中門辺りには足を踏み込みませんでしたが、裏中門辺りの楓もみじ谷は天守台、粟積櫓台より上空の紅葉を楽しみました。
もみじまつり前日-8/8 紅葉編に続く。
+ 続きを読む