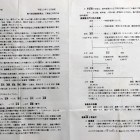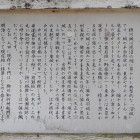境目七城の残り3城です。
いずれも城びと未登録、遺構もほぼ残っていません。
加茂城
周囲は民家と水田になっています。
備中高松城の南に位置し、道には二ノ丸跡の案内板があります。
ここから入っていくと少し高まりとなっている部分があり、説明板が立っています。
秀吉の備中攻めの際、城中での内紛もあり落城したとのこと。
周囲を見渡すとこの城が沼地にあったことがうかがえます。
日幡城
足守川の土手に沿った位置にあります。
石材店(閉まってるかも)があり、石碑が2つ立っています。
その裏手の山が城跡のようですが藪で恐らく私有地。
眺めるのみとしました。
松島城
川崎医科大学の東側にある小山が城跡のようです。
ここも大学の私有地で立ち入り出来ません。
遺構ものこっていないようでもあり遠景のみで退散しました。
当時はこの周辺は海だったとのことです。
とりあえずこれで境目七城を制覇、山〜沼地〜海と結ぶ防衛線を感じることができました。
この日のお昼は岡山グルメのえびめしを。
スパイシーで美味しかったです🦐
【見どころ】
・各城の立地から想像する防衛ライン
+ 続きを読む