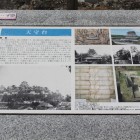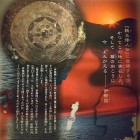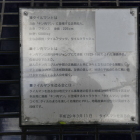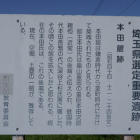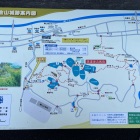「山城に行こう!2024 ぎふオシロフェス」に行ってきました。城びとでも既に何人か投稿されているようです。初日はタイヤをスノータイヤに履き替えていたので岐阜県に着いた時には午後になっていました。
多治見でタイルマンを拝んだ後、今城と久々利城に行って通行証をゲット。久々利城訪問は時間の都合で後日に回して、通行証2枚を持って会場へ。
通行証2枚持参で、特典の「縄張りキャップ」と交換できますが、色が2種類あって悩む。本当は両方欲しいけどベージュを選択し、初日はこれで終了。道の駅「可児ッテ」で一晩過ごします。
翌日は朝一で久々利城を訪問して会場にいくと、すでにかなりの行列が出来ています。世の中にこれだけ山城好きがいるとは・・普段、山であまり人に会わないので正直意外でした。まあ、山城にもよるのですが。
午前10時半より学芸員と例の御三方によるシロトークを拝聴し、午後14時からは御三方と香川元太郎氏による「城好きおやじ三人組と香川元太郎が描く”城”の歩き方」を拝聴しました。
御三方とは、落語家の春風亭昇太師匠と、日本城郭教会学術委員会副委員長の加藤理文氏、滋賀県立大学名誉教授の中井均氏です。
昇太師匠は東海大学に復学されていて、いま4年生で、学割が効くらしいです。教室に昇太師匠がいるってなんか楽しそうです。講演の内容もなかなか楽しめました。
ひとしきりプログラムが終了した後は、余った時間で金山城に行って、二日間の予定は終了です。
+ 続きを読む