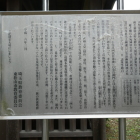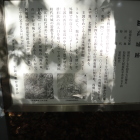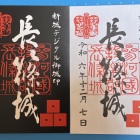香川県の城びと登録物件コンプリートを目指して小豆島へと渡りました。四国行きの定番・前日夜8時前に家を出て淡路SAで仮眠をとり、早朝に高松港にアクセスして高速船に乗船。土庄にてレンタカーを借り受け、皇踏山城に直行しました。野外活動センターからすぐにアクセスできると高をくくっていたのですが、入り口はチェーンで封鎖されていたので、近くの路傍スペースに車を停め、そこから歩いて登城したら結構な歩きでがありました。展望所が二ヶ所あり、小豆島の観光スポット・エンジェルロードを俯瞰することができます。石塁も結構な長さがあり、山頂からの眺望もなかなかのものでした。すっかり時間をかけてしまい、午後には徳島で献血の予約を入れてあったので、星ヶ城の攻城は断念。それでも帰りがけ、晴天の下でエンジェルロードを堪能することができたので満足です。ピクミンブルームの山デコの白ピクミン(皇踏山)まで手に入れることができました。
+ 続きを読む