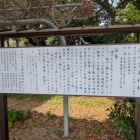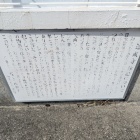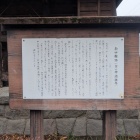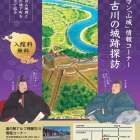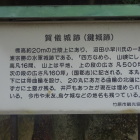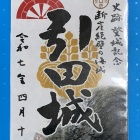日本全国の橋は、日本橋(橋の起点)方面が漢字表記、日本橋逆方面がひらがな表記となっている(とタモリかキンシオが言っていたような)。じゃあ、日本橋はどうなっているのかと言うと、両サイドが漢字ひらがな両面表記という起点ならではの唯一の扱いになっていることに感動する。
ちなみに、「日本橋」の字を書いたのは徳川慶喜でかなり達筆。東京五輪の突貫工事で「日本橋には空がない」と批判されるが、2040年には地下化で空が誕生するようで、まだまだ変貌する江戸城下町を見届けたいと思った次第。
※ 日本橋は錦絵に多く描かれているので関心あれば国会図書館サイトで
https://www.ndl.go.jp/landmarks/sights/nihonbashi/
+ 続きを読む