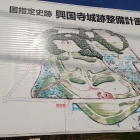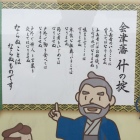私の知る限り、最も高いところに所在する城はこの御坂城かと思います。2年越しでこの城の攻略をねらっていて漸く念願が叶いました。天下茶屋から標高1596mの御坂山を越えて主郭部分の御坂峠まで70分の表示がありましたが、私は45分で到達。標高の高いところに居住しているため空気の薄さもさほど気になりませんでした。御坂山側の郭は複数の堀切での防御。そこから御坂峠に向けて長大な竪堀が続いて横堀となっています。南西側の郭に向けても長大な竪堀。こちらの郭は小さいものの虎口状の土塁がきれいです。主郭部分が鞍部で一番低くなっているのはかなり珍しい造りかと思います。この日は、快晴で落葉した樹間からずっときれいな富士山が見えていました。整備された登山道ですが、尾根道の両側は崖になっており危険がないわけではありません。雪が降る前のこの時期は御坂城攻略のベストシーズンだったと思います。強烈な季節風が吹いていてかなり寒くはあったのですが。雨や雪の後の攻城は断念するのが賢明かと思います。
+ 続きを読む