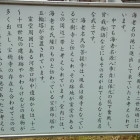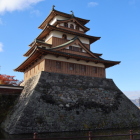今回も100名城から10問です。
写真のお城がどこかわかった方、投稿大歓迎です!
[追記]ヒント出します。
①天守台ではなくて天主台…【安土城】カルビンさん正解!
②はね出し(武者返し)石垣…【人吉城】朝田辰兵衛さん正解!
③月見櫓からの眺め…【松本城】朝田辰兵衛さん正解!
④笏谷石と言えば…【丸岡城】カルビンさん正解!
⑤虎御前山はこの城を攻めるための前線基地…【小谷城】朝田辰兵衛さん正解!
⑥登り石垣があるお城…【伊予松山城】todo94さん正解!
⑦ 鬼門よけのための隅欠(すみおとし)…【上田城】カルビンさん正解!
⑧鯱の門には弾痕が!…【佐賀城】猿さん正解!
⑨お土産は「大手饅頭」…【津山城】todo94さん、猿さん正解!
⑩重臣集めて評定中…【小田原城】チェブさん正解!
ぴーかるさんの問題、岡山城と今治城、行ったことあるのにわからなかったです。
石シリーズこれからもよろしくお願いします。
(ちなみに、今日で籠城21日目です😭)
+ 続きを読む