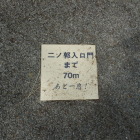一日とことん観音寺城(伝布施淡路丸~伝目賀田丸~裏参道)
(2022/03/20 訪問)
(続き)
裏参道から北東への分岐に入ると、伝布施淡路丸西隅の虎口に至ります。伝布施淡路丸は三方を石塁で囲み、西隅の虎口は端に折れを設けて枡形状にしている…ようですが、崩れていて明瞭ではありません。曲輪内は藪化していて見通しはききませんが、石塁沿いに進んで東隅の虎口から出ると、東に続く尾根に浅くなった堀切が見られました。北辺には尾根を削り残した土塁がそびえ、南東辺と南西辺の石塁からは裏参道を見下ろし、東側からの侵攻に備える曲輪であることがよくわかります。
伝目賀田丸は伝布施淡路丸から裏参道をはさんで南側に広がる曲輪で、西辺と南辺を土塁で囲み、南西隅と東部に虎口が開口しています。南麓からの二つの登城道が合流する曲輪で、南麓への備えとされたと思われます。その他、井戸跡もあるようですが、見落としてしまいました。
伝布施淡路丸と伝目賀田丸の間を少し東に行くと観音正寺の裏参道入口で、表参道側より少し広めの駐車場があります。裏参道から観音正寺までは徒歩10分のなだらかな道で、道中に奥之院の鳥居やねずみ岩、あちこちに石垣も見られるなど、楽々と退屈せずに歩けますので、山上まで車で登るなら裏参道側からがおすすめです。
…ということで、観音正寺から表参道駐車場に戻って約5時間半。できれば御屋形跡や教林坊など城下もめぐりたいところでしたが、時間の都合で今日はここまで。観音正寺と裏参道の南麓にある曲輪群には全く足を踏み入れていませんが、ちょっと寄り道するだけで次々と石垣に遭遇してしまう観音寺城のことですから、今なお数知れない石垣が藪に埋もれたままなんでしょうね。そう考えると空恐ろしいほどです。観音寺城は滋賀県の他の100名城に比べて地味なイメージがありましたが、彦根城のような天守こそないものの、規模や遺構は小谷城にも引けを取らず、安土城より20年も前に総石垣で築かれたとてつもない山城でした。やっぱり日本五大山城ともなると半端ないなぁ…。
+ 続きを読む