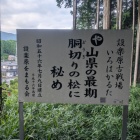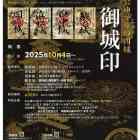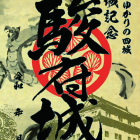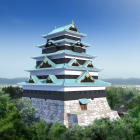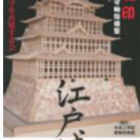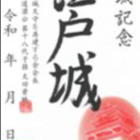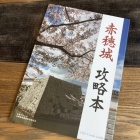大阪・関西万博で大坂城の残念石トイレを見てきました。
当初は万博にほとんど興味がなく、周囲の評判を聞いて興味が出てきた頃には暑すぎて行く気になれず、やっとましになってきたかな、という頃には入場予約が取れなくなっていましたが、何とか最終日前日に駆け込みで行ってきました。
文化財ともいうべき大坂城の残念石をトイレに使うとは何事か! という批判もありましたし、残念石なんて城好きしか興味を示さないのでは? とも思いましたが、現地で見てみると、矢穴もくっきりのこり、なかなかお洒落にデザインされていて、閉幕後に元あったところ(木津川市の赤田川)に戻されるのであれば、藤堂高虎に切り出されてから約400年を経て、こうして一世一代の注目を集めるのも残念石にとって悪くはなかったのかな、とも。できれば全体像などもっといろんな角度からの写真も撮りたかったんですが、女性も多く並んでいるトイレの写真を撮りまくるのはさすがに憚られました…。
パビリオンの予約も取れず、コモンズをはしごするくらいでしたが(でも初めて名前を知った国がいくつもあって非常に興味深かった)、大屋根リングにガンダムに万博グルメに花火にドローンショーにと、家族と万博を満喫した一日でした。
+ 続きを読む