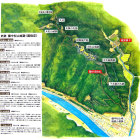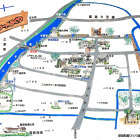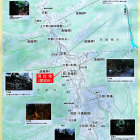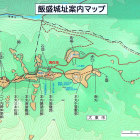築城400年祭特別公開筋鉄御門・鐘櫓
(2022/08/28 訪問)
福山城築城400年祭イベント当日、天守閣のリニューアルオープン日に合わせ各櫓が公開されて居ました、特に筋鉄御門と鐘櫓は伏見櫓と同じく、運良く内部見学が出来ましたので投稿致します。
筋金御門は、福山城本丸の大手に当たり西向き建つ櫓門です、国の重要文化財指定され江戸期からの現存です、名前の通り門扉に筋金が張られて大手の要とした風格です、櫓部は白漆喰仕上げで、今回のリニューアルオープンに合わせ白漆喰の化粧直しがされて真新しく綺麗に成って居ました。
内部は通路部のみ板張り、左右の南側と入口の北側は土間のたたきに成って居ました、今まで見てきた櫓門の内部は全面板敷しか見ていなかったので、こうゆう土間仕様もあるのかと納得、櫓石垣台の上が土間仕様。
以前より筋鉄御門外桝形の多聞櫓復元計画が有ったようですが松も切られて発掘調査して復元かな?と思ったのですが、案内係の方に伺うと遅れている様子、まだはっきりしないのかも? 復元されると筋鉄御門、伏見櫓の間に白漆喰の多聞櫓が入り素晴らしく絵に成るのですが・・待たれます。
鐘櫓は伏見櫓の北側、元御台所門南に現存鐘櫓として残って居り、市の重要文化財に指定されて居ます、二階建て二階部は東側に片寄って居ます、二階部に鐘がぶら下がって鐘が自動で突かれています、現在は午前6時、正午、午後6時、午後10時に時を告げてる福山の名物名鐘です。全国の現存建物では珍しい櫓です。
特別公開資料、見学を運良く導いてくれた方々に感謝いたします。
+ 続きを読む