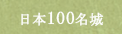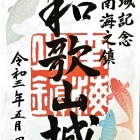県民のほとんどにとって和歌山城は「徳川御三家の城」ですが、昨年あたりからは大河ドラマにちなんで地元でも「豊臣兄弟が築いた城」としてPRされています(さすがに大河ドラマ館とまではいきませんが)。ということで、仕事で近くに行ったついでに「月影の男紀行」として豊臣期の和歌山城をめぐってきました。
和歌山城は羽柴秀吉が紀州攻めの後、雑賀衆らに睨みをきかせるべく羽柴秀長に築かせた城で、ほどなくして秀長が大和郡山城に移ると桑山重晴が城代となり、関ケ原の戦い後に浅野幸長が入城するまでの約15年間桑山氏が城代を務めました。ここでは秀長の築城時と桑山氏による改修をあわせて豊臣期和歌山城とします。なお、豊臣期の呼称はほとんど伝わっていないようなので、本丸や天守曲輪などは浅野期以降の呼称によります。
さて、まずは岡口門から入城。現存する岡口門は徳川期のものですが、豊臣期には岡口門の位置に大手門があったようです。岡口門から三ノ丸を抜けて表坂を上って行くと、右手に本丸(豊臣期二ノ丸)南面の石垣が続き、南東隅部の石垣の下には岩盤が露頭しています。和歌山城は虎伏山と呼ばれる緑泥片岩(紀州青石)の岩山に築かれているため、あちこちに岩盤の露頭が見られます。松ノ丸から本丸表門を抜けた先には二段に積まれた高石垣が広がり、180度ターンして進む間に石垣の上から狙われ放題であることを感じます。
現在の天守曲輪は豊臣期には本丸と呼ばれていて、北西部に小さな天守が建てられていたようです。現在は天守曲輪の周囲を外観復元された連立式天守群が一周していますが、改修はされているとしても天守曲輪(豊臣期本丸)の石垣は豊臣期からのもので、随所に転用石が用いられています。天守曲輪北面の転用石は立ち入り禁止で見られませんが、大天守南東隅の袋狭間の下に見える明らかに色の違う石材は転用石だと思われます。それにしても、近隣で石材が採れない大和郡山城に転用石が多いのはともかく、岩盤を削ればいくらでも採石できるはずの和歌山城で転用石を運んでくる必要ある? と思っていたら、築城前の虎伏山には寺院があったとされ、寺院を移転させた後に残った石を転用したと考えられるんだとか。なるほど、削り出すより既にあるものを転用するほうが手っ取り早いということですか。
裏坂を下りていく途中にも転用石や岩盤の露頭が見られます。裏坂を下りたところには浅野期以降に台所門が設けられ、豊臣期の緑泥片岩の野面積石垣に和泉砂岩の打込接石垣を継ぎ足していることがはっきりとわかります。そして本丸北面の石垣から天守曲輪北面の石垣を眺めて歩き、浅野期に拡張された鶴ノ渓から虎伏山の南側へ。天守曲輪西面の石垣は浅野期のものなので今回はスルーして、天守曲輪南面から松ノ丸南面にかけての二段に積まれた高石垣を眺めました。平たく剥離する緑泥片岩による野面積のため高く積むのは困難ながら、二段に積むことによってかなりの高さになっています。
そして岡口門に戻って豊臣期和歌山城をひとめぐり。他の城だとぱっと見だけで築城・改修時期を判別するのは難しいですが、和歌山城は緑泥片岩の野面積石垣は豊臣期、和泉砂岩の打込接石垣は浅野期か徳川期、花崗斑岩の切込接石垣は徳川期と、私などの素人目にもわかりやすいのがありがたいですね。
+ 続きを読む