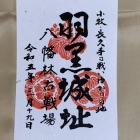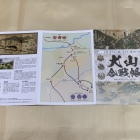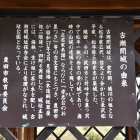金沢城 平城じゃない 尾山城
海鼠壁 ワイドに広がる 金沢城
菱櫓 前田の匠 金沢城
噴水も プールも楽し 金沢城
一句目
写真だけ見て、完全に平城だと思い込んで行った金沢城
けっこうな丘にある平山城で、びっくりしたのが良い思い出です
尾山城の名前を知っていたら誤解しなかったのにと思います
上、中、下の全てに城と言う字を入れて遊んでみました
二句目
五十間長屋、三十間長屋の美しい海鼠壁を詠みました
三句目
一見しただけでは分からない80度と100度の角度をつけた菱櫓
目立たない部分ながら、前田家の職人の技術の高さを感じます
目立つ部分にしたいなら上五を「橋爪門」に替えても良いですね
四句目
兼六園には日本で1番で古い噴水があります
電気は使わず、上にある池との高低差を利用しているというのは驚きです
一方、プールは21世紀美術館の現代アート「スイミングプール」金沢城に行ったら、一度は寄りたい場所です
+ 続きを読む