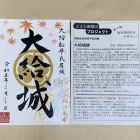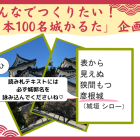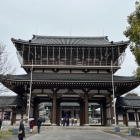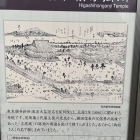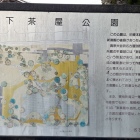さっそく多くの方にご投稿いただき、本当に嬉しく思っております。
どうもありがとうございます!
でも目指すは100城分!
引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。
絵札用の写真ですが、対象によっては縦のほうが美しい、横のほうが適している等もありますし、
遊ぶ際、絵札が縦横混在ゆえの取りづらさも面白いかと思っていますが、
もしかすると、縦横統一するかもしれません。
縦横統一するとなった場合は、採用写真はトリミングさせていただく可能性がありますので、
ご了承いただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
追伸:トク様、ご質問いただき、ありがとうございました!
+ 続きを読む