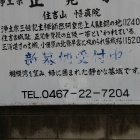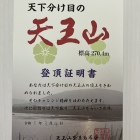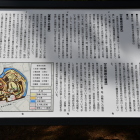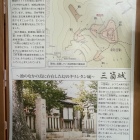ぴーかるさん。
アガリのお城は特別なお城!
100名城のラストは
“地元の松本城”
“現存天守の丸亀城”
と仰った方々を思い出しました。
ヘタレな私は大変そうなところを後回しにしてしまっています。。。
大阪府コンプカウントダウン、噛み締めてくださいませ。
ヒロケンさん。
絶対に寒いとわかっていても長野県には冬に行きたくなるのです。そして凍えながら雪だるまをつくる⛄️
楽しいです(o^^o)
みなさまもぜひ⛄️⛄️
朝田さん。
先だって教えてくださっていた三井記念美術館の〈どうする家康〉特別展に、本日行ってまいりました。久能山東照宮の所蔵品、各種屏風絵、肖像画などなど2時間くらい楽しみました( ´ ▽ ` )ノ
年パスを買ったのでまた見に行きます(^-^)/
+ 続きを読む