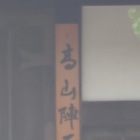【勝山城】
<駐車場他>勝山市役所駐車場
<交通手段>車
<感想>越前ちょこ城巡りの旅ラストの11城目。勝山城は1580年に柴田勝家の甥(のち養子)の柴田勝安によって築城されます。江戸時代には結城秀康の子らが入封されますが、移封されると廃城になり勝山藩は天領となり陣屋が置かれます。1691年に小笠原氏が2万2千石で入封し築城許可が出て再び築城を開始します。小笠原氏は明治維新まで続き維新後に建造物は取り壊しや払い下げられました。勝山城の位置は現在の勝山市役所の辺りで昭和40年頃まで天守台と石垣が残っていたようで、市民会館建設に伴いその時取り壊されたそうです。
先に城跡の位置・形状も全く異なる模擬天守のある勝山城博物館に行って御城印購入、入館しようかと思ったら入館料1000円の高さ(重文でもないのに)に驚き止めました。しかし模擬天守の巨大さには驚かされ、お金かかっているなあと感じます。一応一見してもよいかと。
次に勝山市役所に城跡碑を撮影しに行ったら、なんと満車!?市民会館で荻野目洋子さんのコンサートを開催していたそうで、駐車もできず道路脇に停車しダッシュで撮影して終了しました。帰路は頭の中でダンシングヒーローがグルグル回っていました( ;∀;)。
これにて今回の旅終了、各御城印の購入(open時間帯)に合わせてちょこ城を北から南下していくルートで巡り、小丸城で終了予定でしたが時間が相当余ったので急遽、伊自良氏館と勝山城を入れ込みました。蓮如の城郭寺院始まりの地である吉崎御坊や府中三人衆という単語も初めて知ったので新鮮でした。631㎞無事走破。
<満足度>◆◇◇
+ 続きを読む