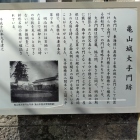比較的近場ながら行けてませんでした。亀山城と言うと、「堀尾氏が丹波亀山城と間違えて伊勢亀山城の天守を解体してしまった」、というのが有名ですが、多門櫓の道向かいの説明板に、「真偽のほどは定かではない」とあって、えー、そうなんって、なりました。天守を解体したこと自体はあったが、間違えて解体したのではないかもなんでしょうか? それとも天守を解体したこと自体が疑問符なのでしょうか。
亀山古城跡に建つ亀山市歴史博物館に亀山城のジオラマがあるとのことで、まず向かったのですが、博物館法改正に伴い、資料のデジタル化を進めるために、今年10月1日から2027年3月31日まで閉館ですと。入り口扉からジオラマが見えるかと覗いてみましたが、見えませんでした。
亀山というと亀山ローソクも有名です。亀山ローソク工場の敷地にある亀山ローソクタウン(ショップ、ローソク作り体験、ローソク展示)に寄りました。ローソクを使うシーンは減ったことから、ショップは、フレグランス、お香も大々的に取り扱ってました。LED模擬ローソクも各種。
+ 続きを読む